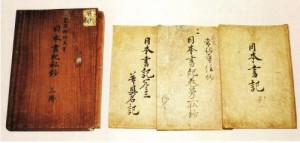三徳山投入堂 08-May

鳥取県三朝町の 三徳山投入堂 は一度はいってみなければと思っていた、奇観である。寺伝によれば、慶雲3年(706年)に役行者(えんのぎょうじゃ)が三枚のハスの花びらを散らし、「仏教に縁のある所に落ちるように」と祈ったところ、その一枚が三徳山(みとくさん)に落ち開山したと伝えられる修験道場ということだ。三朝町から奥に5kmほど車で登ってゆくと、すでに多くの観光客が行きかって賑わっている。一番奥の駐車場に止めて、さっそく食堂に入りそばで腹ごしらえをして寺に入山した。階段をしばらく登ると本堂に到着、さらに「投入堂」への登山のための入り口がある。靴のチェックと名前を記入していよいよ登山開始だ。
さすがに、今日は祝日のせいか大勢のひとが列をつくっている。われわれのように登山モードの人は少なく、普段着の人がほとんどである。なかには多分、ハイヒールできたに違いない若い女性もいる。じつは入り口で靴が不適切とされると、有料で「わらじ」を履かなければならないのだ。この「わらじ」がどうやらすべりにくいらしい。中途半端な運動靴ではよくすべるようで、慎重さにかける若い人がよく転倒していた。

さすがに修験道場らしくきびしい登りがつづく、手を掛けて登る場所が多いのでお年寄りなどで、あきらめて帰る人もいる。情報として記しておくが、後半の鎖場以外では最初のあたりが一番きびしいので、ここだけのりきれば、あとはいけると思う。が、自信のない人はあきらめなさいという配慮なのかもしれない。
約40分で目的の「投入堂」に到着する。こんな絶壁にこんなものがというだけで「びっくり」であるが、実は以前、中国へ旅行した際「大同」でほとんど同様の懸空寺という寺が観光地としてあり、そのときはそのお堂の中に入れた経験があった。お参りをすませると下山であるが、もちろん下りの方が危険なのでゆっくりとおりる、登りとほぼ同じ時間で登山口に到着し無事「三徳山」登山は終了した。









 ここには「上東遺跡の護岸跡」「吉備の陶棺」「吉備特殊器台」などの大物を見ることができる。さて教えてもらった道をゆき約20分ほどで矢藤冶山古墳の頂上に到着した。実際にはセンターの事務の女性はこの古墳のことを知らなかったし、リンクページをさがしたがWEB上にこの古墳を説明するページはヒットしない、つまり思いのほか扱いがちいさいのだ。しかし墳長約35mの前方後円墳で方格規炬鏡(TLV鏡)1、大型硬玉勾玉1、ガラス小玉50、終末期の特殊器台と特殊壷が多数発見され最古式のものとかんがえられるというのだからミッシングリングともいうべき非常に重要な遺跡であるに違いないのだ。奈良大和に特殊器台が移動する直前のものとすれば史上最古の前方後円墳である可能性もある。
ここには「上東遺跡の護岸跡」「吉備の陶棺」「吉備特殊器台」などの大物を見ることができる。さて教えてもらった道をゆき約20分ほどで矢藤冶山古墳の頂上に到着した。実際にはセンターの事務の女性はこの古墳のことを知らなかったし、リンクページをさがしたがWEB上にこの古墳を説明するページはヒットしない、つまり思いのほか扱いがちいさいのだ。しかし墳長約35mの前方後円墳で方格規炬鏡(TLV鏡)1、大型硬玉勾玉1、ガラス小玉50、終末期の特殊器台と特殊壷が多数発見され最古式のものとかんがえられるというのだからミッシングリングともいうべき非常に重要な遺跡であるに違いないのだ。奈良大和に特殊器台が移動する直前のものとすれば史上最古の前方後円墳である可能性もある。