梅原猛 の足跡を追って
大神は私たちに試練を与えた? 2010年3月22日
 実は約一月前の2月11日(建国の日)、降りしきる雨の中を私たちは出雲弥山の麓の道をこの社を求めて歩いていた。出雲井神社である。司馬遼太郎氏の「生きている出雲王朝」に紹介される古代出雲の語り部W氏が継承の儀式を行う舞台とされる神社だ。
実は約一月前の2月11日(建国の日)、降りしきる雨の中を私たちは出雲弥山の麓の道をこの社を求めて歩いていた。出雲井神社である。司馬遼太郎氏の「生きている出雲王朝」に紹介される古代出雲の語り部W氏が継承の儀式を行う舞台とされる神社だ。
吉田大洋氏の著書から引用すると「私は出雲市を訪れたとき、ひょんな体験をした。クナトノ大神を祀る出雲井神社(いづもいかみのやしろ)に寄ってみようと思い、出雲大社の社務所で道をたずねた。ところが、なかなか教えてくれないのである。うさん臭そうに、こちらの顔を眺めながら、「なぜ、そんなところへ行くんですか。小さな社がポツンと立っているだけで、なんにもありませんよ」と言う。道順を聞き出すのに、五、六分も押し問答をしなければならなかった。社家では出雲井神社と聞いただけで、神経をビリビリさせるのである。社家にとって、出雲井神社を訪れる者は、危険人物なのであろう。出雲井神社は、出雲大社の東、宇伽(うが)山のふもとの竹薮に、ひっそりと忘れられたように建っていた。」というくだりがある。
我々は出雲国造北島家(出雲教)の駐車場に車を停めてHPで仕込んだ「東へしばらく」という情報を頼りに歩いた。車がやっと一台通れる細い道だ、数百メートルのあいだに小さな社が幾つかある、どれもネットで紹介されていたものと風情がちがう、真名井と呼ばれる湧水泉をとおりすぎ、業をにやしてこの豪雨の中だれかに訊ねることにした。

ちょっとした集会所のようなところにいた数人のおばさまたちに聞いてみた。「そんな神社はここらにはないなあ」「うん、ないない!」という返事であった。もう少し行くと弥山登山口がありそこで気持ちが折れた。「もうこの辺であきらめよう、寒いし、もう靴がぐちょぐちょ!」そして、先ほどの集会所にもどるともう誰もいなかった、我々はどうも歓迎されていないように感じる雨であった。
ひと月が過ぎ春となった、今日は天気もよい、12時に北島家に着き、車を右折させるとそのままその細い道を進んでいった。前回あきらめた地点から約200mでこの「出雲井神社」はひっそりと佇んでいた。ひと月半をかけての到着であった。
「クナトノ大神」は大国主よりも古い出雲族の祖神とされる神で、天孫族によってその正体を隠されたと考えられている。熊野大社の「亀太夫神事」の不思議さも、須佐之男の「八俣の大蛇」の謎もすべてこの「クナトノ大神」の存在で説明されるというのが前出の吉田大洋氏の著書「謎の出雲帝国」の中で語られている。これについての考察はまた改めてトライしてみたい。
今日の目的はこれでほぼ達成された感じである、いつものように大社西にある「荒木屋」にむかい昼食とした。

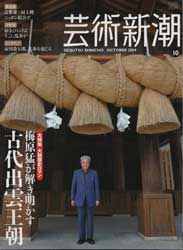 先日の播磨訪問に続いて、本番ともいえる出雲訪問、最初は前回訪れた
先日の播磨訪問に続いて、本番ともいえる出雲訪問、最初は前回訪れた その母刺国若比売(さしくにわかひめ)は泣き泣き天に上って神産巣日之命(かみむすびのみこと)に訴え、キサガイ比売(赤貝)とウムギ比売(蛤)を遣わされた。その貝殻を削った粉を清水で母乳のように練って塗ったところ蘇生して「麗しき壮夫(をとこ)になりて出で遊行きき。」とある。「伯伎国の手間の山本」を現在地(寺内字久清)として赤猪岩神社は祀られている。また日本洋画の巨人青木繁の「大穴牟知命」 (大国主命の受難の物語)という作品はこのエピソードをテーマとしている。
その母刺国若比売(さしくにわかひめ)は泣き泣き天に上って神産巣日之命(かみむすびのみこと)に訴え、キサガイ比売(赤貝)とウムギ比売(蛤)を遣わされた。その貝殻を削った粉を清水で母乳のように練って塗ったところ蘇生して「麗しき壮夫(をとこ)になりて出で遊行きき。」とある。「伯伎国の手間の山本」を現在地(寺内字久清)として赤猪岩神社は祀られている。また日本洋画の巨人青木繁の「大穴牟知命」 (大国主命の受難の物語)という作品はこのエピソードをテーマとしている。
 それが下級神官にボロクソに言われるのを、じっと我慢しなければならないのだ、この神事の不思議さにこそ出雲の謎を解く鍵が隠されている。
それが下級神官にボロクソに言われるのを、じっと我慢しなければならないのだ、この神事の不思議さにこそ出雲の謎を解く鍵が隠されている。
 勝田郡勝央町勝間田というのは中々説明がむずかしいが、湯の郷の北西にある町で津山、奈義、湯の郷の真ん中といったところだろうか。勝間田駅の駐車場らしき広場の端っこにある。店内はとてもしゃれていて若い主人やスタッフが元気よく、とても活気を感じる若々しい店だ。料理も充分レベルを保っているし、石釜もありおいしいピッザもいただける。県北のドライブで寄るにとても良いお店を発見したという感じ!
勝田郡勝央町勝間田というのは中々説明がむずかしいが、湯の郷の北西にある町で津山、奈義、湯の郷の真ん中といったところだろうか。勝間田駅の駐車場らしき広場の端っこにある。店内はとてもしゃれていて若い主人やスタッフが元気よく、とても活気を感じる若々しい店だ。料理も充分レベルを保っているし、石釜もありおいしいピッザもいただける。県北のドライブで寄るにとても良いお店を発見したという感じ! 「昭和30年代、蒜山高原では、各家庭で工夫して調合した、タレで焼そば、ジンギスカンなどを食べることがブームになっていました。
「昭和30年代、蒜山高原では、各家庭で工夫して調合した、タレで焼そば、ジンギスカンなどを食べることがブームになっていました。

 鳥取砂丘から東に10kmほどの網代漁港、「浦富海岸島めぐり遊覧船のりば内」にあるのが「あじろや」である。イカが豊富にとれる網代漁港ならではのイカ料理や、海産物を使った定食などがリーズナブルに味わえる。しかしここの刺身に眼もくれずこの「イカスミカレー」をいただく。鳥取B級グルメの代表格のカレーだが、この店だと海の幸もカレーも頂けるという便利さそして気軽さである。
鳥取砂丘から東に10kmほどの網代漁港、「浦富海岸島めぐり遊覧船のりば内」にあるのが「あじろや」である。イカが豊富にとれる網代漁港ならではのイカ料理や、海産物を使った定食などがリーズナブルに味わえる。しかしここの刺身に眼もくれずこの「イカスミカレー」をいただく。鳥取B級グルメの代表格のカレーだが、この店だと海の幸もカレーも頂けるという便利さそして気軽さである。




 田村氏はその仕事の傍ら独自の斬新な古代史解釈に没頭し多くの著作を残した方である。「古事記は事実であった」という原点から、佐竹先生の「高天原蒜山高原説」を支持し、古事記に著された神話をこの蒜山(吉備ー美作)から伯耆、出雲にかけての歴史に基づいた伝承であるという説を唱えられている。特に地図を丹念に精査されることが大きな特徴で、今回その内の代表的な場所を実際に訪ねてみることにした。
田村氏はその仕事の傍ら独自の斬新な古代史解釈に没頭し多くの著作を残した方である。「古事記は事実であった」という原点から、佐竹先生の「高天原蒜山高原説」を支持し、古事記に著された神話をこの蒜山(吉備ー美作)から伯耆、出雲にかけての歴史に基づいた伝承であるという説を唱えられている。特に地図を丹念に精査されることが大きな特徴で、今回その内の代表的な場所を実際に訪ねてみることにした。

 なぜなら、そのゆったりとした起伏、その背景にそびえる山々、畑にそだつ作物や芝そしてすこしひんやりとした空気が蒜山そっくりなのだ。つまり高天原天孫族が蒜山から降りてこの地を選んだ様子がありありと思い浮かぶのである。左の写真はこの高千穂より西南を望む大山の姿だが、ご存知のとおり大山は富士山のような円錐形ではなく頂上はぎざぎざでいくつものピークがある。つまり、大山こそが高千穂なのだ。
なぜなら、そのゆったりとした起伏、その背景にそびえる山々、畑にそだつ作物や芝そしてすこしひんやりとした空気が蒜山そっくりなのだ。つまり高天原天孫族が蒜山から降りてこの地を選んだ様子がありありと思い浮かぶのである。左の写真はこの高千穂より西南を望む大山の姿だが、ご存知のとおり大山は富士山のような円錐形ではなく頂上はぎざぎざでいくつものピークがある。つまり、大山こそが高千穂なのだ。