倭文 神社は織物の神様 07-Dec.18

倭文 と書いて「しとり」(しどり、しずり)と読み、古代日本製の絹などの織物を指す。右写真は鳥取県倉吉市の東にある東郷湖のほとりに静かに建つ伯耆一宮 倭 文神社である。このおりは単に一宮巡りの一環として午に鳥取の宇部神社を訪ねた後、午後日の傾きかけた頃に到着した時のもので、当時読み方もご祭神などの由緒も知らぬ状態であった。がしかし、ここがことのほか重要な場所であることにやっと気がついた。
我々がぼんやりと習ってきた日本の歴史といえば、先進文化はすべて中国朝鮮から学んだものですべてに遅れていたと、そう思い込んでいた。しかし、そう単純なものでは無さそうだ。まず言葉(言語)の問題を探ってみた、すると日本語は北方民族系で、バイカル湖周辺を出発点とした言語に近く、その文法のうえにアジア南方系の単語が進入融和してできているという。つまり思いのほか中国語、朝鮮語との関係が薄く、 文化的かつ政治的に中国、朝鮮の圧倒的影響を受け入れたのであれば、日本語はもっと別のものになっていたはずなのだ。縄文時代から北方南方の文化を基盤として大陸文化を消化してきたといえる。そんな中、秦の始皇帝が蓬莱の国(理想郷)と信じ、不老長寿の薬をもとめて徐福を送り込んだのが倭であるが数千人も連れてきたというから、これは使節というより進駐軍か移民団のようなものだろう。これが秦氏のはじめで機織り(ハタオリ)を伝えたという説などもある。一般的には神功皇后が導入し仁徳天皇が国中に広め振興したというのが定説だが、それより前から倭(日本)で上質の絹織物が生産されていたのではと思う。
文化的かつ政治的に中国、朝鮮の圧倒的影響を受け入れたのであれば、日本語はもっと別のものになっていたはずなのだ。縄文時代から北方南方の文化を基盤として大陸文化を消化してきたといえる。そんな中、秦の始皇帝が蓬莱の国(理想郷)と信じ、不老長寿の薬をもとめて徐福を送り込んだのが倭であるが数千人も連れてきたというから、これは使節というより進駐軍か移民団のようなものだろう。これが秦氏のはじめで機織り(ハタオリ)を伝えたという説などもある。一般的には神功皇后が導入し仁徳天皇が国中に広め振興したというのが定説だが、それより前から倭(日本)で上質の絹織物が生産されていたのではと思う。
過去、岡山の久米郡(現津山市、美咲町)に倭文村(現津山市油木)が存在した、ちなみに隣が大倭村(やまと)である。ここに延喜式内社ではないが、倭文神社がある。(Wikipedia)で倭文神社をみると全国に十七社が書かれておりそのほとんどが現在も繊維産業の盛んな場所で、古代より倭文部の粗神である「建葉槌命(天羽雷命)」を奉ったもの、この倭文神社も同様で、なんとすぐ隣の字(地名)が「桑」である。
「こんな田舎にもその昔は繊維産業があったのか!」というだけではないことが「久米郡史」に書かれていた。倭文五社弊頭為貞國太夫より神祇官への書状に「当社は人皇十代崇神天皇の七年十一月丁卯、神地神戸を定められ、この時よりの御鎮座に御座候」とある。また、本多応之助の「 倭文 往来」の中に「往昔は日止里神社と称し奉り。倭文本宮と唱え尊崇し奉ると旧記にこれあり、何時頃に至りて五宮と席下り、其のいわれ知るべからず。」となっている。つまり、十代崇神天皇の七年十一月(紀元前後の弥生?古墳時代)にできて「倭文本宮」と呼ばれていたということになる。

ここ久米から北に上り奥津を経由、または湯原(神湯村)を経由して川沿いに日本海に向かうとそこには東郷湖(池)がある。つまりここ大倭の倭文を積んだ貿易商隊(キャラバン)が積出港である東郷湖に向かう姿がはっきりと見えてきた。[この説は新しい日本の歴史に詳しく説明されています。]
奈良の葛城にも倭文神社(葛木倭文坐天羽雷命神社)がある、そのHPで全国の倭文神社の根本社と名乗り、その背後の当麻寺で有名な二上山の雄山を神奈備山としている。そのサイト内に倭文サミットに関する愉快なエピソードが載っている、つまり他の倭文神社がここを根本社とは思っていないのだ。普通同じ名前の神社の場合由緒の中に「どこそこから勧請された」と書かれているケースは多い。じつはここ久米倭文神社の南にも同じ二上山があるのだが偶然ではなさそうだ。(右写真はその中腹にある真言宗「両山寺」である)
二上山の東南の麓に「誕生寺」というお寺があるが、この地に生まれた浄土宗法然上人にちなんだ寺で法然上人霊蹟一番札所である。そして九番札所が「当麻寺奥の院」で葛城の二上山にある。法然は美作国久米(現在の岡山県久米郡久米南町)の押領使、漆間時国(うるま ときくに)と、母、秦氏君との子として生まれるのだが、この秦氏の祖は仁徳朝阿知使主が率いた漢民で、技術にすぐれ綾錦(あや)の姓を賜った。このとき秦の一族は綾錦の長となり、部民を率いて美作国久米郡に移った。法然上人の母はその一族から出た人といわれる。(浄土宗大辞典より)。つまり仁徳云々はともかく法然は秦氏(倭文部)の血を引き、なぜかその二つの二上山の麓に倭文神社がある。そして盆地をはんだ反対側には三輪山があるのだ。
こうしてまた、吉備と奈良に共通の名前が現れた、そして私の直感ではあるが、葛木倭文坐天羽雷命神社が全国の倭文神社の根本社ということはない!



 このあたりの話はとんでもなくわかり難いのだが、系図をみると兄弟従兄弟同士が争い何人もが殺されてしまう。そして25代武烈につづき謎だらけの継体天皇へとつながる訳である。
このあたりの話はとんでもなくわかり難いのだが、系図をみると兄弟従兄弟同士が争い何人もが殺されてしまう。そして25代武烈につづき謎だらけの継体天皇へとつながる訳である。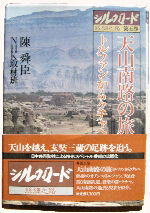








 文化的かつ政治的に中国、朝鮮の圧倒的影響を受け入れたのであれば、日本語はもっと別のものになっていたはずなのだ。縄文時代から北方南方の文化を基盤として大陸文化を消化してきたといえる。そんな中、秦の始皇帝が蓬莱の国(理想郷)と信じ、不老長寿の薬をもとめて徐福を送り込んだのが倭であるが数千人も連れてきたというから、これは使節というより進駐軍か移民団のようなものだろう。これが秦氏のはじめで機織り(ハタオリ)を
文化的かつ政治的に中国、朝鮮の圧倒的影響を受け入れたのであれば、日本語はもっと別のものになっていたはずなのだ。縄文時代から北方南方の文化を基盤として大陸文化を消化してきたといえる。そんな中、秦の始皇帝が蓬莱の国(理想郷)と信じ、不老長寿の薬をもとめて徐福を送り込んだのが倭であるが数千人も連れてきたというから、これは使節というより進駐軍か移民団のようなものだろう。これが秦氏のはじめで機織り(ハタオリ)を

