「 ツモロ 」のハンバーグは覚悟がいる! 07-Apr.24

知る人ぞ知る「岩石ハンバーグの店ツモロ」(勝手に命名)は岡山市の国道2号線(旧?)上道北方ナカシマプロペラの前にある懐かしい喫茶店の風情を残す店だ。懐かしいのも当然で私が車を乗り始めた頃からすでにそこにあった、つまり34年前以前からその場所にあり当時すでに幻の名車といわれていた「いすずベレット」がいつも停まっていたことを思い出す。
現在は情報誌などで「600gのビッグハンバーグ」の店として紹介されており、私も挑戦はしたがとてもしんどかった思い出がある。本日は家内と二人だからそんな無理はせず、「カレーとビーフシチュー」を注文した。 見てお分かりになるかどうか、キャベツが別の皿に一盛りできてさらにそこに焼き肉が4切れほど添えられている。「絶対に量で不満はいわせない!」という店主の強いメッセージが現れているようだ。
見てお分かりになるかどうか、キャベツが別の皿に一盛りできてさらにそこに焼き肉が4切れほど添えられている。「絶対に量で不満はいわせない!」という店主の強いメッセージが現れているようだ。
我々がその大振りなわりに意外なほど繊細な味を賞味している間、次々と客が現れる。そしてそのほとんどが「ハンバーグ」を注文する。そんな様子をみて家内がいった「ここのお客さんはみんな同じような体格してるわね!」そのとおり、店内にいる男性客で僕が一番スリムなような気がした。
「カレーとビーフシチュー」でそれぞれ¥1000


 もともと古代においては女性の役割であったというのが自説であるので、昨年はじめてお会いしたおりには「我が意を得たり」とおおいに気を強くしたものだ。
もともと古代においては女性の役割であったというのが自説であるので、昨年はじめてお会いしたおりには「我が意を得たり」とおおいに気を強くしたものだ。



 小生の愚説ではあるが、弥生墳丘墓とその祭器をみていると「出雲と吉備」は強く深い連帯関係にあり、後に大和勢力と合従連衡ないし拡大していくなか、それぞれの神がそれぞれ小競り合いを経て一つの伝説にまとめられたのだと考える。つまり「八岐大蛇伝説」は吉備の神話ではないのか!故にそれに由来する箇所が多数存在するではないだろうか。
小生の愚説ではあるが、弥生墳丘墓とその祭器をみていると「出雲と吉備」は強く深い連帯関係にあり、後に大和勢力と合従連衡ないし拡大していくなか、それぞれの神がそれぞれ小競り合いを経て一つの伝説にまとめられたのだと考える。つまり「八岐大蛇伝説」は吉備の神話ではないのか!故にそれに由来する箇所が多数存在するではないだろうか。



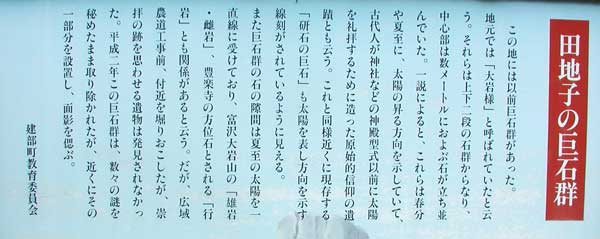
 北島三郎の 醍醐桜 の唄をBGMに畑のなかをその巨大な桜にむかって近づくと右にある二代目もずいぶん立派になっていた。
北島三郎の 醍醐桜 の唄をBGMに畑のなかをその巨大な桜にむかって近づくと右にある二代目もずいぶん立派になっていた。



